2025年4月1日から「育毛読書」と題して、週に1冊本を読む習慣を始めました。週に2〜3冊読むことも珍しくなく、多くの知識を得ているはずでした。しかし、心のどこかで「本当にこれでいいのかな?」という戸惑いを抱えていたのも事実です。
本を読むことは素晴らしい体験です。新しい知識は世界を広げ、思考を深めてくれます。でも、その知識を本当に自分のものにできているか?と問われると、自信がありませんでした。読み進めれば進めるほど、「わかったフリ」をしている感覚が拭えなかったのです。
そんな時、以前購入した松浦弥太郎さんの著書『考え方のコツ』を久しぶりに開いてみました。そこに書かれていたのは、まさに私の悩みを改善させるヒントが書かれていました。
それは「思考の時間を確保する」という、ごくシンプルながらも本質的な教えです。
「思考の時間」があなたの読書を変える
松浦弥太郎さんは、1日に2回、意図的に思考の時間をスケジュールに組み込んでいるそうです。
そのやり方はこんな感じ。
- A3サイズの白い紙を1枚用意する。(著者はA3を推奨)
- テーマを決める。
- インターネット検索は禁止。
松浦さんは「検索エンジンに依存し、考えることなく答えを得ようとすると、人間として大切な機能が失われていく」と述べています。
これは耳が痛い話ではないでしょうか。私もついつい、自分の頭で考える前に「答えらしきもの」をネットに頼りがちです。これでは、本当に考える力は衰えていく一方ですよね。
思考は、簡単には前に進まないかもしれません。それでも諦めずに、制約を設けずに思考の流れに身を任せることが大切だと松浦さんは言います。
単語でも雰囲気でも、浮かんできた断片を、とにかく白い紙に書いていきましょう。これは頭の中で整理されていない感情や感覚のようなものを、視覚化していくプロセスです。
「わかったフリ」から「本当にわかる」へ
私の悩み、「読書で得た知識を吸収できていない」という問題は、まさにこの「思考の時間」をショートカットし、「わかったフリ」をしているだけだったことに気づかされました。わかったフリのまま次の本へ手を伸ばすから、深く吸収できるはずがありません。
本を読んで知識を得る。 その内容をメモに残す。 これらはもちろん大切な工程です。
しかし、本当に重要なのはそのあと。 「思考の時間を設ける」という工程を、私は怠っていました。「週に1冊読まねば!」という思い込みが、いつの間にか読書の質を下げていたのです。
自分の内側と真正面から向き合うのは勇気がいる。しかし、ここで怯んでは思考のプロセスをたどることはできません。
今週の育毛読書からは、読むペースを少し落とし、思考の時間を十分に確保することにします。
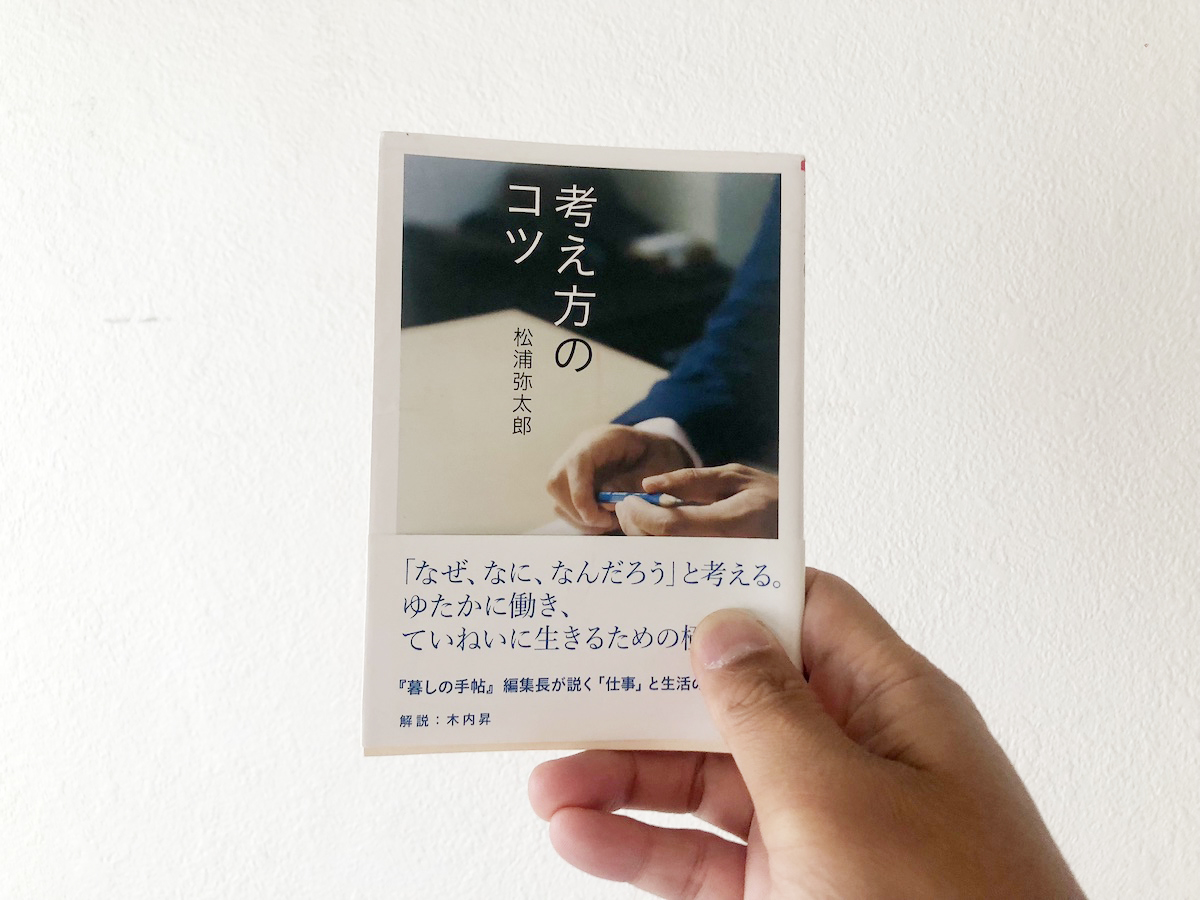



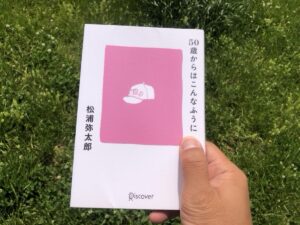
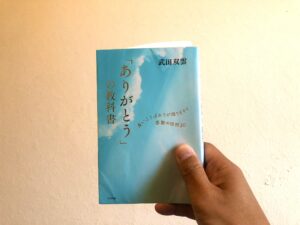
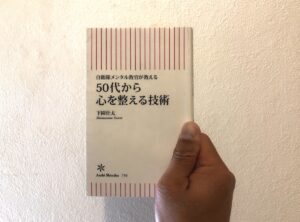
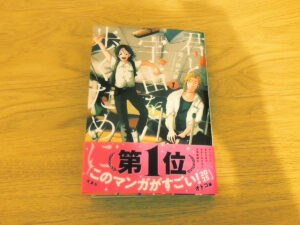

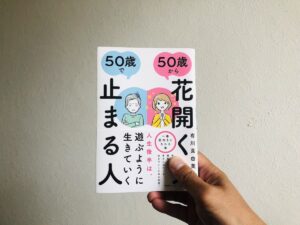

-300x225.jpg)